東京芸術劇場の開場
若杉弘指揮、東京都交響楽団のベートーベンの第9の響きで東京芸術劇場大ホールのオープニングコンサートがスタートした。建設工事の遅れはあったものの、予定通り10月30日、開場記念式典が行なわれ、都響、シノーポリ指揮+フィルハーモニア管弦楽団の16日間全曲演奏のマーラー・チクルス、マゼール指揮+フランス国立管弦楽団等の演奏会が続いている。もうすでに演奏会に行かれた方もおられよう。
この劇場は東京都が池袋駅西口に建設したもので、1982年の総合芸術文化施設建設懇談会の答申の基本構想をもとに、1985年~1987年の基本、実施設計、1987年~1990年の建設工事期間を経てオープンした。建築設計は芦原建築設計研究所で、当事務所は1985年の基本設計半ばより参加してきた。

JR池袋駅を降り、西口広場に向かうと大きなアトリウムを持つ建物が目に付く。これが芸術劇場である。アトリウムに入ると上下にエスカレータが走り、各ホールへとつながっている。これまでの劇場とは異なり、このように大、中、小ホールが積層する形で配置されているのも特徴である。劇場は基本構想の“多くの都民が、優れた音楽、演劇、舞踊等の舞台芸術を鑑賞するとともに、都民自らが芸術文化の創造活動ができる施設であること”を基本的な柱とし、つぎのような施設により構成されている。
- 大ホール:本格的なコンサートホール(2017席)
- 中ホール:演劇を中心とし、オペラ、バレエにも対応した劇場(850席)
- 小ホール:2つの実験的な創造活動のできる小劇場(300、450席)
- リハーサル室:音楽、演劇、舞踊の練習(6室)
- 展示ギャラリー:各種芸術、資料等の展示
- 集会室:大、中、小の会議室(9室)
各施設の概要、経過等はこれまでにも紹介してきた。また、まだ開場したばかりということからコンサートホールの演奏会、演劇ホールの観劇の印象記は別の機会にして、ここでは、音響設計のとくに重要な課題の幾つかを紹介する。音響設計部門としてはつぎのようなことが課題であった。
- 敷地に近接する地下鉄からの騒音の防止
- 各種施設の音響的な隔離
- コンサートホールの音響
- 新しい劇場としての電気音響設備
(1)(2)についてであるが、敷地端を地下鉄有楽町線が東西にかすめる形で通っているため、基本設計当初のホールの配置計画では、多くの時間をその影響の検討に費した。敷地および近接の既存建物における地下鉄騒音、振動の調査、影響予測と対策の検討にはじまり、各室間の遮音性能確保との兼合いからの検討も行なった。この結果、コンサートホールをできるだけ地下鉄構築から離すこと、低減効果、施工性等の面から対策の採り易い小ホール、リハーサル室に遮音性能の確保も含め、浮き構造を採用することとした。このことがホールを積層にした一因でもある。竣工時の地下鉄騒音の測定結果では、地下鉄軌道に最も近い地下2階のリハーサル室(浮き構造採用)でNC-15以下、各ホールでもNC-15以下という地下鉄騒音を検知できない結果であった。また、ホール間、リハーサル室間の遮音性能は、ほぼ80~100dB(500Hz)と設計当初の目標値をクリアーしたものであった。
つぎの課題は、大ホールが約2000席のコンサート専用ホールとしていかに良い室内音響条件を確保できるかということであった。これについては、室形状、客席配分からの検討が中心で、設計段階では、設計に活用しはじめたコンピュータシミュレーションによる初期反射音の時間、空間分布に着目した検討と従来の1/50の光学模型実験による反射音分布の確認という作業を交互に進め、構造等に関わる骨格を決定して来た。そして、施工初期の段階で、設計期間中に実施できなかった1/10の音響模型実験により、内装の詳細形状の確認を行なうという方法を採用してきた。このホールは、ステージエンド型のホールという設計条件と、欧米のオペラハウスのように客席内が取囲まれたような、客席同志が向かい合うような客席空間、オルガンステージの下に光庭の見える開口を設けたいという建築設計の意図した室形をもとに、ステージ上部に大きな可動の反射板を設置すること、ワインヤードの考え方にもとずく客席配分を採用することにより十分な初期反射音の確保を目指した。また、響きの質の面では、上野の東京文化会館の重厚で暖かみのある響きをこのホールの規模に合った形で実現することを意図した。これについては、残響時間の周波数特性にも着目し、内装構造にも注意をはらった。これまでの演奏会からの印象では、意図した方向にあると思っている。赤坂のサントリーホール、渋谷のNHKホール、オーチャードホール等、雰囲気、響きの特色も異なるこれらのホールでのコンサートが楽しみになってきた。オルガン工事の関係もあって最終的な値ではないが、参考までにホールの残響時間を図−1に示す。
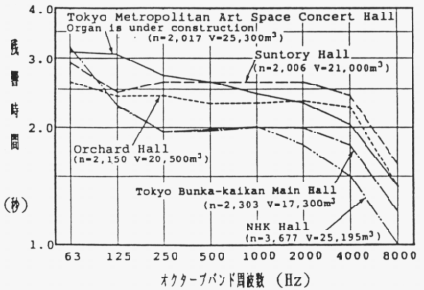
最後に、中ホールについて少し触れたい。中ホールは、国内でも最大規模を誇る舞台設備を備えた劇場として建設された。このため、電気音響設備についても、コンピュータ化とともに、新しい機能の充実にも力をいれた。その一つにDelta Stereophony Systemがある。出演者の動きに応じた音の定位を意図したものである。スピーカの仕込み、音像の大きさの制御、ソフトの点からまだまだとの意見もあるが、効果音の再生には、リアルで強力なものになるとの印象を持っている。これからの機能の活用と発展に期待したい。芸術劇場については、たくさんの施設、設備があり、話題のパイプオルガンなどまだまだ記したいこともある。また機会があれば紹介したい。(池田覚 記)
ウィーン国立歌劇場フルデジタル調整卓導入
9月1日からウィーン国立オペラ劇場で世界初のフルデジタル音響調整卓が稼働を始めた。このフルデジタル音響調整卓は実は日本製であり、TOA(株)がウィーン国立オペラ劇場の主席トーンマイスターであるヴォルフガング・フリッツ氏との共同作業によって開発・製作したものである。今回、我々はウィーン国立オペラ劇場でその音響調整卓が稼働している現場を視察する機会を得たのでその概要を紹介する。
まず、オペラハウスとしてのウィーン国立オペラ劇場の音響設備は基本的に効果音に限って使用されている。これは、生のオーケストラ・歌等に相応する自然な再生音を得るために大型のスピーカシステムがプロセニアム全周、ホリゾントバック、客席天井中央(シャンデリアの周り)等に配置されている。これらの効果音の再生にはテープレコーダの再生音だけでなく、オーケストラピットに入り切らない楽団員、大型の楽器(パイプオルガン等)や自然効果音用道具およびバンダなども含まれている。一方、これらの各所に散らばった楽団員や劇場の運営・進行スタッフに適切な指示を行うための設備、モニター設備も膨大な規模となっている。
これらの大規模な効果音の設備の問題は、操作を間違えやすいことと機器の操作に紛れて肝心のオーケストラや歌との調和する効果音を再生することに集中できないことなどであろう。「トゥーランドット」の演目では上演中に100か所に及ぶ調整量の変更・切替があり、改修前の調整卓ではこの操作に3人もの技術者を要するそうである。このような複雑な操作をレパートリーシステムを採っているがゆえに毎回セットするのも大変な作業である。旧来の調整卓でも一部分の自動化は行われていたが、今回のフルデジタル調整卓の導入によりこの複雑な調整量の変更・切替作業の省力化が飛躍的に改善されている。また、演目の日変りメニューにおいても最適な入出力構成に変更できるフレキシビリティも備えている。このフルデジタル調整卓は256の入力と256の出力を持つミックスシステムである。この範囲の機器と接続ができ、調整系も64×48の入出力マトリクスを持ち、フェーダーは130mmストロークのムービング型である。これらの接続ポイントおよび音質、音量等の設定値はすべて記憶され再現できるものである。
今回の「欧州舞台音響研修ツアー」には当社より浪花、稲生の2名が参加した。各劇場の電気音響設備の中でも、特に興味をもち期待をしていたものがこのウィーン国立オペラ劇場のフルデジタル調整卓の稼働状態であった。同劇場を視察した日の夜「トスカ」を観賞した結果は、我々の心配をよそにまったく何事もなかったようにスムースに上演を終えてしまった。デジタル音響機器特有のノイズ、クリック音等のトラブルらしい物は何一つとして聴取されなかったのである。今ここで世界に冠たるウィーンの国立オペラ劇場で日本の、それも世界初の劇場用フルデジタル音響調整卓の成功を目の前にした。この感激は一生忘れられないであろう。なお、2号機のウィーンの国立ブルク劇場への導入が決定し、現在調整室の新設も併せて設置工事中である。この音響調整卓の特徴の一つにコンピュータのソフトウエアの変更で機能が更新できることがある。従来のようにハード(機器)がソフト(機能)をあまり制限しないのである。これが重要であるが、この考え方が広く受け入れられるものかどうか今後注目していきたい。(浪花克治 記)
ボストン・シンフォニーホール訪問記
1990年10月14日、偉大な指揮者であり、また作曲家でもあったバーンスタインが亡くなった日にボストンに着いた。つぎの日の朝刊の第一面にはその訃報が大きく報じられ、TVでも関係者へのインタビューを盛込んだ特集が各局で放送されていた。1週間の滞在中に私たちが聞いたほとんどのコンサートでは、哀悼の意が込められたメッセージや演奏がはじめに献じられた。また、エィブリー・フィッシャーホールでのニューヨークフィルの定期では急遽、予定していた曲目がすべてバーンスタイン作曲のものに変更されるなど、バーンスタインがアメリカの音楽界にとっていかに偉大な存在であるか、そしてその急逝を悼んでいるかを肌で感じることができた。

今度の旅行は、現在設計を進めている墨田区文化会館の意匠と音響のデザインコンセプトをより具体化することが目的で、ボストン・シンフォニーホールをはじめカーネギーホール、エィブリー・フィッシャーホール、また評判の高いソルトレイクシティのシンフォニーホールを訪れた。その中でもボストン・シンフォニーホールは、墨田区文化会館の基本モチーフであることから、その視察と音を聴くのが何よりも第一の目的であった。
ボストン・シンフォニーホールでは、小澤征爾:指揮、M.アルゲリッチ:ピアノ、ボストン・シンフォニーオーケストラ(BSO)演奏のプロコフィエフのピアノ協奏曲3番、シューベルトの交響曲9番を聴くことができた。アルゲリッチの演奏は息をのむほど素晴らしく、そしてBSOの音は非常に繊細でバランスの良い響きであった。同じ演奏者による同じ曲目の演奏をカーネギーホールで幸運にも聴けたのだが、その響きは明らかに異なっていた。カーネギーホールの響きは非常に明るく、それなりに素晴らしいものであったが、小澤=BSOの響きは、やはりボストン・シンフォニーホールとの組合わせがベストだと思われた。ホールとオーケストラ、やはり密接な関係にあることを痛感した。
ボストン・シンフォニーホールは、よく知られているように、室形状はシューボックスである。幅が狭く、客席後壁から舞台への距離はかなり遠い。客席の壁は後壁も含めてどこも堅く、レンガの上にプラスター塗りのようである。舞台の壁はボードで、それ程厚いものとは思われない。舞台の床も同様でそれ程厚くはないが堅そうである。壁は、写真でみるとフラットのようであるが、彫刻が置かれたり、細部に細かな装飾が施されたりで、かなり凸凹している。客席の椅子は木製の可動床に置かれており、夏期のポップスコンサート時には取除かれてフラットになるようになっている。その可動床はボコボコで、歩き難さを補うためかカーペットが敷かれている。椅子もレザー張りで豪華なものではない。これらの何が良い音をつくりだしているのか?いずれもが重要な役割をもっているのだろう。意欲の駆立てられる旅だった。(福地智子 記)